- ホーム
- 不動産相続の基礎知識・やるべきことチェックリスト
目次
不動産を相続する前に知っておきたい基本と準備
不動産の相続は、突然起こることも多く、「何から手をつければよいか分からない」という方も少なくありません。
こちらでは、相続登記や認知症による手続きへの影響、今からできる備えについて、プロの視点から丁寧にご紹介いたします。大切な不動産を守るために、まずは基礎から一緒に確認してみましょう。
「いしばし不動産相続相談室」では、札幌市を中心に、江別市・石狩市・小樽市など近隣エリアに対応。査定依頼・相談は無料で承ります。
はじめに知っておきたい不動産相続の基礎知識
不動産を相続する際には、知っておくべきルールや注意点が多くあります。トラブルを防ぎ、スムーズな手続きのために、まずは基本的な知識を確認しましょう。
相続とは?

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、配偶者や子どもなどの法定相続人が引き継ぐことを指します。
相続の対象となるのは、不動産や預貯金、株式、借金など多岐にわたり、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産(借金・ローンなど)」も含まれます。
不動産が関わる相続の場合は、名義変更(相続登記)をおこなう必要があります。
また、複数人で遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になることも多く、話し合いがまとまらないケースも見られます。
生前贈与とは?

生前贈与とは、亡くなる前に財産の一部を家族などに譲ることを指します。
相続が発生する前にあらかじめ財産を分けておくことで、遺産分割時のトラブル防止や、相続税対策として活用されることが多い方法です。
たとえば、不動産を子どもに譲りたい場合、贈与契約を結び、登記名義を変更することで、生前に所有権を移すことが可能です。
ただし、贈与には「贈与税」が発生する場合があり、特例や非課税枠の活用も含めて、制度の理解が重要です。
また、生前贈与をおこなったとしても、相続時に「特別受益」として相続財産に加算されることもあり、家族間での話し合いと記録の整理が不可欠です。
Pick up相続と生前贈与の違い
相続と生前贈与の違いをまとめると、以下の通りです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 相続 | 生前贈与 | |
|---|---|---|
| 財産が移るタイミング | 被相続人の死亡後に移転 | 生前(贈与者が生きている間に)移転 |
| 主な手続き内容 | 相続登記、遺産分割協議、相続税申告など | 贈与契約書の作成、登記変更、贈与税申告など |
| 税金の種類 | 相続税(基礎控除あり) | 贈与税(年間110万円まで非課税、その他特例あり) |
| 家族間の調整 | 複数の相続人で分割協議が必要になる場合もあり | 財産を渡す相手を自由に決められる(後のトラブル回避に) |
| 手続きの難易度 | 不動産が含まれると複雑になりやすい | 手続き・税務ともに専門的な知識が必要 |
| 向いているケース | ご逝去後に公平に分けたい場合 | 争続を防ぎたい、あらかじめ財産を整理しておきたい場合 |
不動産が関係する場合は、どちらの選択にも専門的な判断が求められます。
「うちの場合はどちらがよい?」とお悩みの方は、どうぞお気軽に「いしばし不動産相続相談室」までご相談ください。無料相談にて、お客様の状況に応じたアドバイスを丁寧にご案内いたします。
Pick up2024年4月から相続登記が義務化へ
放置は過料の対象になることも

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合は、所有権を取得した日から3年以内に登記申請が義務付けられました。
この制度は、過去に相続した不動産も対象となるため、長年登記を放置していた場合も注意が必要です。
「名義変更をしていないけれど、今のところ困っていない」と感じていても、そのまま放置すると将来的に売却や名義変更ができず、相続人間でのトラブルを引き起こす原因になります。
また、正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産が複数人で相続されている場合や、遠方にある物件などは、手続きが煩雑になることもあります。
相続後はできるだけ早めに対応し、安心して管理・売却できるよう備えておくことが大切です。
登記の流れや必要書類について不安がある方は、どうぞ「いしばし不動産相続相談室」へご相談ください。専門家が丁寧にサポートいたします。
Pick up認知症になる前に!早めの対策が安心につながります

認知症を発症すると、法律上「意思能力」がないとみなされ、契約や法律行為が無効となる場合があります。
意思能力とは、自分の行為の結果を理解し、判断する能力のことです。
この能力が欠如していると、遺言書の作成や不動産の売買契約などが無効となる可能性があります。
対策として、意思能力があるうちに「成年後見制度」や「家族信託」を利用することが有効です。
- 成年後見制度…裁判所が選任した後見人が、財産管理や契約行為を代行できる制度です。
- 家族信託…信頼できる家族に財産の管理を託すことができる制度です。
認知症の進行により、これらの手続きができなくなる前に、早めの準備が重要です。
相続や財産管理について不安がある方は、専門家に相談することをおすすめします。
当相談室では、相続税に詳しい専門家と連携し、皆様のご相談を承っております。オンラインでの相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
認知症によって不動産相続でできなくなること一覧
| できなくなること | 認知症になるとできなくなる理由・内容 |
|---|---|
| 遺産分割協議への参加 | 法的な意思表示が必要なため、本人が同意・署名できなくなります。 |
| 相続登記の申請 | 名義変更は本人の申請が前提。意思能力がないと手続きが進められません。 |
| 不動産の売却契約 | 売買契約には本人の意思確認が必要。契約が無効になるおそれがあります。 |
| 生前贈与・信託契約の締結 | 財産を託す・譲る契約は本人の判断が必要。認知症後は契約そのものが不成立に。 |
| 遺言書の作成 | 有効な遺言には作成時点での明確な意思能力が求められます。 |
| 不動産の管理・税金支払いなど | 維持管理や固定資産税の手続き判断ができなくなり、放置や滞納のリスクが高まります。 |
このような事態に備えるには、成年後見制度や家族信託の活用が有効です。
不動産をお持ちの方は、早めの対策をご検討ください。当相談室では、制度の説明から手続きまで、専門家と連携して丁寧にご案内いたします。
知っておきたい「相続税と贈与税の違い」とは?

相続や生前贈与に関するご相談をいただく中で、「相続税と贈与税の違いがよく分からない」というお声をよく耳にします。
こちらでは、それぞれの税金の基本的な仕組みや対象、そして両者の違いについてご説明いたします。
「相続税」とは?
相続税とは、亡くなった方の財産を相続や遺贈によって受け取った場合に課される税金です。
対象となる財産には、不動産、預貯金、有価証券、現金、さらには借地権や車なども含まれます。
基礎控除が設けられており、一定の金額を超えた場合に申告・納税が必要となります。
相続発生後10か月以内に、申告と納税をおこなう必要があります。
「贈与税」とは?
贈与税とは、生前に財産を無償で受け取った場合にかかる税金です。
個人から個人への贈与に対して課税され、年間110万円を超える金額については原則課税対象となります。
対象となるのは、現金、不動産、株式、車など、多様な資産です。
特例として「住宅取得等資金の非課税制度」や「相続時精算課税制度」などがあり、計画的な活用が求められます。
相続税と贈与税の違い
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 相続税 | 贈与税 | |
|---|---|---|
| 税金がかかるタイミング | 被相続人が亡くなった後 | 生前に財産を譲り受けたとき |
| 対象となる財産 | 不動産、現金、預貯金、有価証券など | 不動産、現金、預貯金、有価証券、動産など |
| 基礎控除額 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 年間110万円(一般贈与) |
| 申告・納税期限 | 相続開始から10か月以内 | 翌年の2月1日〜3月15日まで |
| 節税対策の例 | 配偶者控除、生命保険の非課税枠、小規模宅地の特例など | 非課税制度の活用(住宅資金贈与・教育資金贈与など) |
不動産が含まれる場合、税務判断が特に複雑になります。ご自身にとって最適な対策を講じるためにも、当相談室へお早めにご相談ください。
Pick up生前贈与の対象期間が7年に延長
相続税の実質増税に注意

2023年度の税制改正により、相続税の課税対象となる「生前贈与加算期間」が、これまでの3年から7年へ延長されました。
これにより、亡くなる前7年以内に贈与された財産は、原則として相続財産に加算されることになります。
この改正は、相続税対策として生前贈与を検討している方にとって、実質的な増税となる可能性があり、特に高額な不動産や複数年にわたる贈与には注意が必要です。
誤った判断で贈与を進めてしまうと、かえって税負担が大きくなることもあります。
当相談室でも、信頼できる税理士と連携し、ご相談を承っております。制度の詳細や対策について、お気軽にご連絡ください。
「遺言書があるかどうか」で相続の進め方は大きく変わります
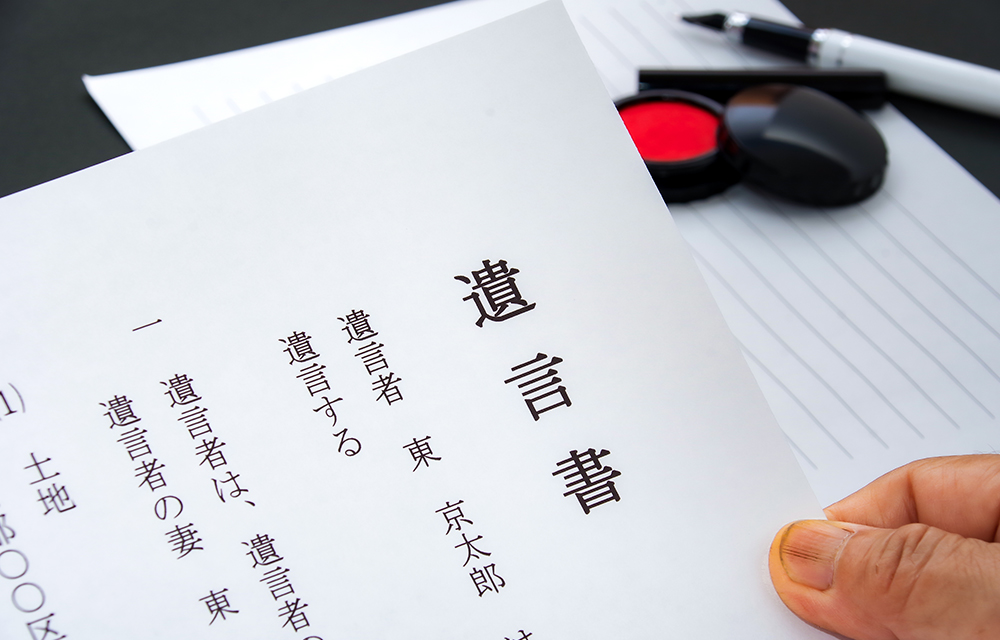
相続の手続きにおいて、まず確認すべき重要なポイントが「遺言書の有無」です。
遺言書があるかどうかによって、財産の分け方や相続手続きの流れが大きく変わるため、最初にしっかり確認することが大切です。
こちらは、遺言書のある場合とない場合の違い、そして「遺産分割協議」についてわかりやすく解説いたします。
遺言書の有無で相続の方法が変わる

相続が発生した際、遺言書があれば、その内容に従って財産の分け方が決まります。
公正証書遺言であればすぐに手続きが可能ですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」が必要となります。
一方、遺言書がない場合には、相続人全員で話し合いをおこない、財産の分け方を決める必要があります。これが「遺産分割協議」です。
遺言書があるかないかは、手続きの難易度や所要期間にも大きく影響します。
遺言書がない場合の「遺産分割協議」とは

遺言書が存在しない場合、相続人全員で集まり、財産の分け方について話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といい、全員の合意がなければ手続きを進めることができません。
分割の対象となるのは、不動産、預貯金、株式、自動車、家財などあらゆる財産です。協議の結果をもとに「遺産分割協議書」を作成し、相続登記や名義変更、金融機関での手続きに使用します。
しかし、相続人の関係性が希薄だったり、感情の対立がある場合には、協議が難航することも珍しくありません。また、相続人が全国に散らばっている場合には、調整に時間と労力がかかります。
そうした事態を避けるためにも、専門家の立ち会いやサポートを受けながら進めることが望ましく、必要であれば家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能です。
遺言書がない場合でも、冷静に手続きを進めるために、当相談室へお気軽にご相談ください。オンライン相談も可能ですので、遠方に住まれている相続人がいらっしゃる場合にも、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
亡くなった直後の相続手続き、何から始めればいい?

ご家族が亡くなられたあと、悲しみの中でも進めなければならないのが、さまざまな相続手続きです。
限られた期間の中で、必要な届け出や手続きをひとつずつ行う必要があり、何から手をつけてよいか分からないという方も多くいらっしゃいます。
こちらでは、死亡後すぐにおこなうべき相続手続きを、わかりやすくチェックリスト形式でご紹介します。
不安な方は、当相談室までご相談ください。丁寧にサポートいたします。
相続発生後のスケジュールとやるべきチェックリスト
| なるべく早く~7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡届は、死亡診断書(または死体検案書)を添付して、市区町村役場へ提出します。提出後に「火葬許可証」が発行され、葬儀や火葬の手続きに進むことができます。 |
|---|---|---|
| 遺言書の有無を確認 | 自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。遺言書がない場合は、相続人全員による「遺産分割協議」が必要となります。 | |
| 10日以内 | 年金受給者の死亡届(受給権者死亡届) | 故人が年金を受給していた場合、10日以内に年金事務所へ届け出ます。提出により、未支給年金の請求手続きも可能です。 |
| 相続人の確定 | 相続関係を明らかにするため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍などを取り寄せて、法定相続人を確定します。 | |
| 14日以内 | 国民健康保険証・ 介護保険証の返却 |
故人が国民健康保険や介護保険に加入していた場合、市区町村役場へ保険証を返却します。 |
| 世帯主変更届の提出 | 故人が世帯主だった場合、同居の家族が市区町村へ世帯主変更届を提出する必要があります。 | |
| 相続財産の調査・ 目録作成 |
不動産、預貯金、有価証券、負債などを調査・整理し、「財産目録」を作成します。これが今後の相続方法(承認か放棄か)の判断材料になります。 | |
| 3か月以内 | 相続の承認または放棄の選択 | 相続人は、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択し、家庭裁判所へ申述します。期限は相続開始を知った日から3か月以内です。 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 故人が個人で所得を得ていた場合(年金・事業収入など)、その年の1月1日~死亡日までの所得を税務署に申告します。必要に応じて納税もおこないます。 |
| 遺産分割協議 | 遺言書がない場合や、遺言で分割方法が指定されていない場合には、相続人全員で財産の分け方を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。 | |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。申告と納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。延納・物納の制度もあります。 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 (必要な場合) |
法定相続人が遺言などにより極端に財産を受け取れなかった場合、「遺留分侵害額請求」をすることができます。行使期限は、相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内です(時効あり)。 |
「何から始めればいい?」を一緒に解決します

相続は突然おとずれることが多く、「何から始めればよいか分からない」という方がほとんどです。
とくに不動産が含まれる場合には、登記や税務、名義変更、遺産分割協議など、専門的な手続きが多く、ご家族だけで進めるのは大きな負担となります。
当相談室では、札幌市を中心に、江別市・石狩市・小樽市・北広島市・恵庭市・千歳市など、近隣エリアの相続相談に幅広く対応しております。
相続発生直後のご相談から、不動産の売却、残置物の片付け、専門家との連携によるワンストップ対応まで、安心してお任せいただけます。
小さなご不安でも結構です。どうぞ、お電話・LINE・メールフォームからお気軽にお問い合わせください。私たち「いしばし不動産相続相談室」が、丁寧にお手伝いいたします。


