目次
GIFT贈与をお考えの方へ|
贈与前にすべき準備・
税金対策
- ホーム
- 贈与をお考えの方へ|贈与前にすべき準備・税金対策
目次
贈与や相続の前にやっておきたい準備と対策
「そろそろ家や土地を子どもに渡したい」「将来の相続トラブルを防ぎたい」と考え始めたら、早めの準備が大切です。
相続や贈与には、法律や税金の知識が必要で、事前の対策によってご家族の負担を大きく軽減できます。
こちらでは、贈与や相続をスムーズに進めるためのポイントや、認知症に備えた対策、相続税・贈与税に関する注意点について、わかりやすくご紹介します。将来の不安を、今から少しずつ整理していきましょう。
相続対策のタイミングとは
贈与を検討している時におすすめのタイミング

相続や贈与の対策は、「まだ早いかな」と思っている段階で始めるのが最適です。特に、財産を譲る側が元気で判断力がしっかりしているうちに行うことで、将来の手続きやトラブルを回避しやすくなります。
贈与は、年間の非課税枠(110万円)を活用して計画的に進めることがポイント。数年かけて段階的に渡す方法も検討できます。
元気な「今のうち」に対策しておいた方が良い理由

相続や贈与の対策は、体調が安定し、判断力がしっかりしているうちに進めることが何より重要です。
たとえば、認知症を発症してしまうと、法律上「意思能力がない」と判断される場合があり、贈与契約や遺言書の作成が無効になる可能性があります。
また、成年後見制度を利用すると、ご本人の財産が自由に動かせなくなるため、贈与や売却などが制限されてしまいます。
元気なうちに準備しておけば、「誰にどの財産を渡したいか」「どのように分けたいか」といったご自身の意思を明確に反映できるだけでなく、相続人同士のトラブルも未然に防ぐことができます。
加えて、生前贈与の非課税枠(年間110万円)を活用した計画的な贈与や、「家族信託」を活用した財産管理対策なども、ご本人が元気なうちでなければ実行できません。
将来に向けて、心身ともに余裕のある今こそが、最も良いタイミングです。
不安な点は、ぜひ当相談室までご相談ください。専門家とともに、安心できる対策をご提案いたします。
Pick up生前贈与は「年間110万円以内」で
計画的に進めましょう

「生前に少しずつ財産を渡しておきたい」――そう考える方にとって、活用したいのが「暦年贈与の非課税制度」です。
この制度では、1人あたり年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。
つまり、たとえばお子さまやお孫さまに対して毎年110万円ずつ贈与していけば、数年かけてまとまった財産を非課税で移転できるのです。
贈与は一括で大きな金額を渡すと税負担が重くなりますが、この制度を活用すれば、税金をかけずに計画的な資産移転が可能になります。
特に不動産の現金化を検討している方にとっては、売却後の資金を分散して贈与することで、節税につなげることもできます。
ただし、2026年からは「相続前7年以内の贈与」が相続財産に加算される制度改正が予定されており、今後はさらに慎重な運用が求められます。
「今のうちに贈与を始めたい」「どのように贈与すればよいか分からない」とお悩みの方は、ぜひ当相談室にご相談ください。
税理士などの専門家と連携し、ご家族に合った贈与プランをご提案いたします。
認知症に備えるための財産管理制度「成年後見制度」と「家族信託」とは

相続や贈与を考えていた矢先に、ご家族が認知症と診断されることは少なくありません。
認知症が進行すると、法律上「意思能力がない」と判断され、不動産の売却や贈与、遺言の作成などが一切できなくなる可能性があります。
こうした事態に備える制度として、「成年後見制度」や「家族信託」が注目されています。
こちらでは、それぞれの制度の特徴や違いをわかりやすくご紹介いたします。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力が低下した方に代わり、財産管理や契約などの法的行為を行う「成年後見人」を家庭裁判所が選任し、支援する制度です。
後見人は本人の代わりに、不動産の売却、預貯金の管理、各種手続きの代行などを行うことができます。
ただし、財産の処分や贈与には制限があり、柔軟な資産運用には不向きな面もあります。
家族信託とは?
家族信託とは、ご本人が元気なうちに、自分の財産を家族(信頼できる人)に託して、代わりに管理・運用・処分してもらう制度です。
契約内容によっては、認知症発症後も資産の売却や贈与などを柔軟に行えるのが大きな特徴です。
信託契約は公的制度ではなく民間の契約によって成り立つため、内容設計の自由度が高く、ご家族の事情に合わせた柔軟な対応が可能です。
成年後見制度と家族信託の違い
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 成年後見制度 | 家族信託 | |
|---|---|---|
| 目的 | 判断能力が低下した人を法的に支援し、財産を保護するため | 元気なうちに財産管理・活用の仕組みを作るため |
| 開始のタイミング | 認知症の診断など、判断能力の低下後に家庭裁判所へ申立て | 判断能力があるうちに契約を結ぶ必要がある |
| 手続きの方法 | 家庭裁判所に申立て。審査・後見人の選任が必要 | 委託者・受託者の契約で成立(専門家のサポートが望ましい) |
| 管理・運用の柔軟性 | 制限あり(原則として財産の維持管理) | 契約内容に応じて柔軟な資産運用・処分が可能 |
| 財産の処分・売却 | 原則として裁判所の許可が必要 | 契約で許可されていれば受託者が実行可能 |
| 家族への贈与 | 原則としてできない(制限される) | 条件を設定すれば可能(信託契約による) |
| 終了のタイミング | 本人が亡くなったときなど | 契約で決めた条件(死亡・一定期間満了など)により終了 |
| 費用・管理の手間 | 裁判所への定期報告・専門家の関与が必要 | 自由度が高く、仕組み次第で管理の手間も軽減可能 |
| 向いているケース | 認知症発症後、第三者の法的支援が必要な方 | 認知症に備えたい、将来の財産承継や活用を考えている方 |
成年後見制度は、認知症などで判断力が低下した後の「法的保護」を目的とした制度であり、財産を守るための仕組みです。
一方、家族信託は元気なうちに契約することで、柔軟な資産管理や活用が可能となる「予防的な仕組み」です。
どちらの制度が合っているかは、ご家族の状況や目的によって異なります。
当相談室では、司法書士などの専門家と連携し、適切な制度選びや導入のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
早めの生前贈与で、相続税の負担を抑えましょう
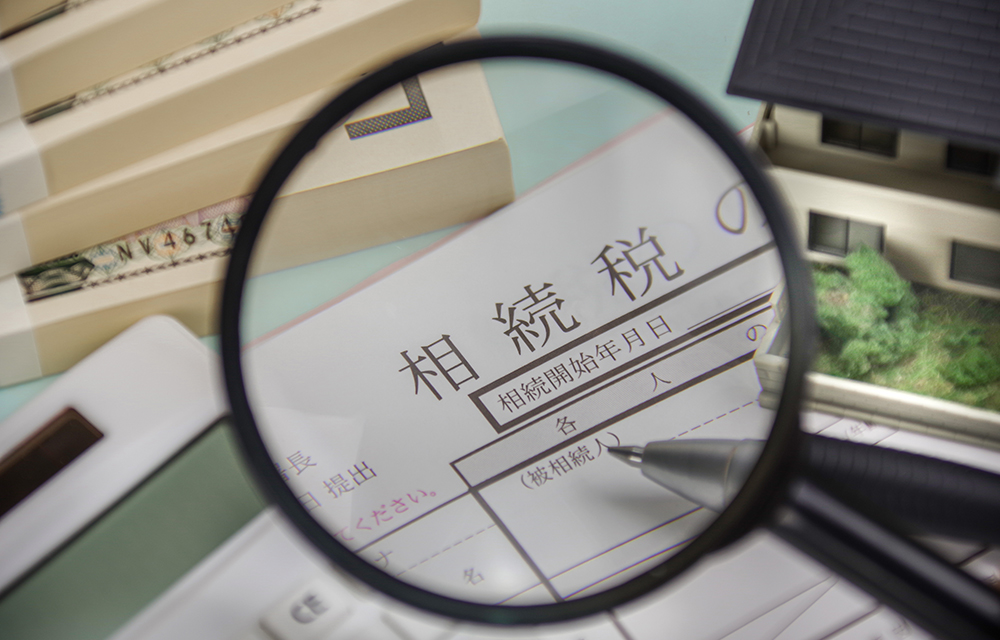
生前贈与は、相続税の課税対象となる財産をあらかじめ分散・縮小させることで、相続税の負担を軽減できる有効な対策です。
たとえば、暦年贈与の非課税枠(年間110万円)を利用すれば、長期間にわたって計画的に財産を移転できます。
さらに、住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与など、一定の条件を満たせば非課税となる特例制度も活用可能です。
相続発生時に想定される税負担を抑えるためには、早めの対策と制度の正しい理解が不可欠です。
当相談室では、贈与と相続のバランスを考えた具体的なご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
生前贈与は計画的に!失敗しないための注意点

生前贈与は、相続税の負担を減らすための有効な手段ですが、制度を正しく理解していないと、かえって税金が増えてしまうリスクもあります。
たとえば、2023年度の税制改正により、2024年以降は亡くなる前の「7年以内の贈与」が相続税の対象に加算されることが決まっています。
また、名義預金(実際には贈与が成立していないと判断される預金)などは、贈与と認められないケースもあります。
制度の変更や注意点を踏まえたうえで、信頼できる専門家と相談しながら計画的に進めることが大切です。
贈与による節税を確実に実現するためには、正しい知識とサポートが欠かせません。
よくあるご質問
- Q生前贈与って、いつから始めたらいいの?
- A贈与は早めに始めるのが理想です。元気なうちに少しずつ贈与することで、非課税枠(年間110万円)を活用し、将来の相続税対策にもつながります。
- Q誰にでも贈与できますか?
- A基本的に個人間であれば誰にでも贈与は可能ですが、相続税対策としての効果を考えるなら、相続人や孫など直系卑属への贈与が一般的です。
- Q贈与税はどのくらいかかりますか?
- A年間110万円までの贈与であれば非課税ですが、それを超えると税率に応じた贈与税が発生します。受け取る人の関係性や金額によって税率が異なります。
- Q現金だけでなく、不動産も贈与できますか?
- Aはい、可能です。ただし、不動産の贈与には登録免許税や不動産取得税などの別途費用がかかりますので、事前の確認が必要です。
- Q名義だけ変えれば贈与したことになりますか?
- Aいいえ。名義変更だけでは贈与と認められない場合があります。贈与契約書の作成や贈与税の申告など、形式を整えることが大切です。
- Q子どもに贈与したお金を親が管理していても大丈夫?
- A原則として、受贈者(子ども)が自分で管理・使用できていることが重要です。親が管理していると「名義預金」とみなされる可能性があります。
- Q生前贈与した財産は、相続時にまた計算されますか?
- A一定の条件を満たすと、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算され、相続税の対象になるため注意が必要です。
- Q教育資金や住宅資金の贈与は非課税って本当?
- Aはい、一定の要件を満たせば特例制度により非課税で贈与できる場合があります。事前に制度内容や申請手続きの確認が必要です。
- Q贈与契約書って作った方がいいの?
- Aはい、贈与の事実を明確にするためにも贈与契約書の作成は非常に有効です。税務署対策としても、書面を残しておくことが望ましいです。
- Q贈与と家族信託は何が違うの?
- A贈与は財産を完全に相手に渡す行為ですが、家族信託は財産を託して「管理・運用」してもらう仕組みです。柔軟な財産管理をしたい場合は信託も検討されるとよいでしょう。
贈与や相続の準備に不安がある方はご相談ください

「いつ、どのように贈与を進めたらいいか分からない」「税金のことが心配」――そんなお悩みは、当相談室にお任せください。
「いしばし不動産相続相談室」では、札幌市を中心に、江別市・石狩市・小樽市・北広島市・恵庭市・千歳市まで対応し、相続・贈与の両面から具体的なアドバイスをご提供しています。
税理士や司法書士など専門家と連携し、ご家族の将来に寄り添った対策をご提案いたします。
小さなご相談からでも構いません。お電話・LINE・メールフォームから、お気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。


